こんにちは。白うさ🐇です。
”離乳食を手作りする”
なんだか心のハードル高くないですか?
今やベビーフードがあるし、それで良くない?
と思っている、そこのあなた!
大賛成です。私も様々なベビーフードを活用しています。
それでも何か手作りしたいな、と思う方に本記事はおすすめです。
離乳食中期で簡単なメニューといえば、ポテトサラダ!
一見、めんどくさそうに感じませんか?
いえいえ、一度作れば簡単でしかもアレンジし放題。
そんなポテトサラダ(ついでに他のメニューも)を紹介します。
この記事で分かること!
- お手軽な調理法
- アレンジレシピ
- 離乳食の簡単保存方法
【本日の献立】
本日のメニューはこちら
- ポテトサラダ
- 野菜の出汁煮
- バナナペースト
食材は以下の通り
- じゃがいも お好みの量
- お好きな野菜 お好みの量
(人参、玉ねぎ、かぶ、ブロッコリー等々) - バナナ お好みの量

★時短ポイント★
この時期は量は食べないので、色々な種類の野菜を一度に煮ると効率的です
流れ図を見てイメージしてみよう
まずは全体の流れの図を見て、並行作業をイメージしてください。
縦方向が時間軸で、メニュー毎に色分けしています。
作業場所を4つに区切って、作業内容を示しています。
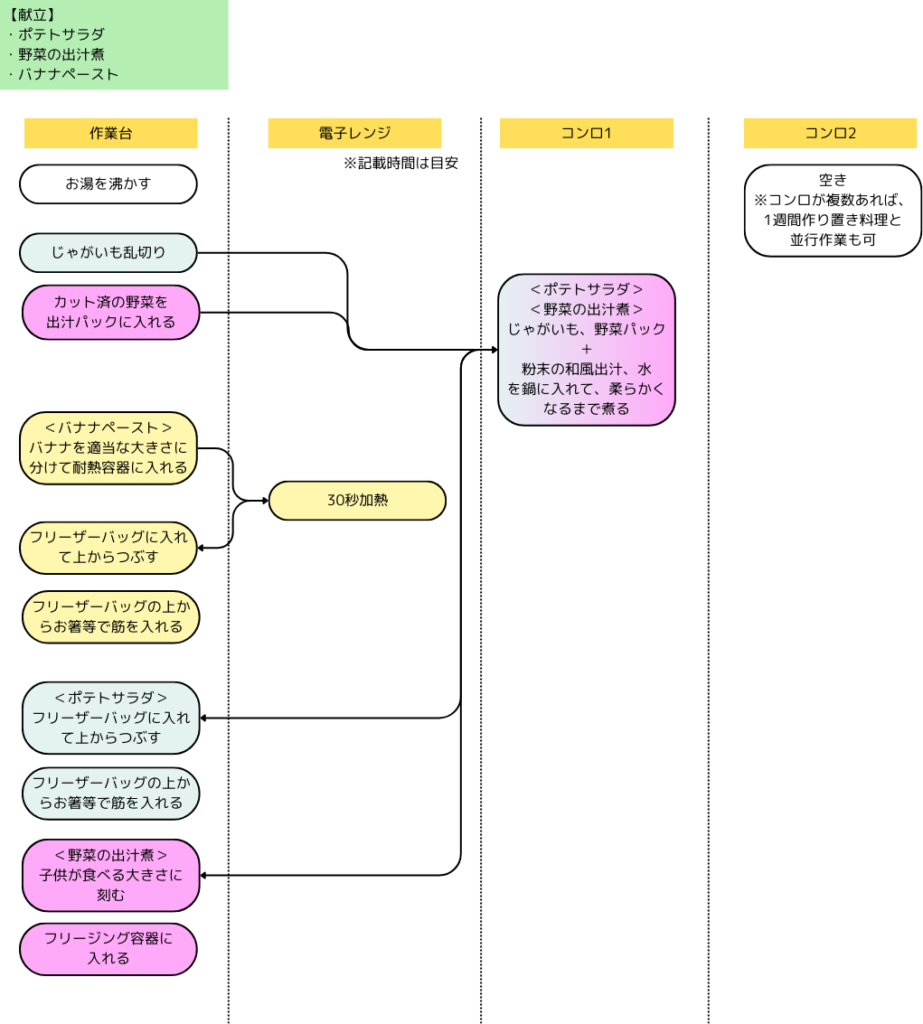
調理工程を詳しく!
では、ここから調理工程を詳しく見ていきましょう。
下準備
お湯をケトルでたっぷり沸かす
★ポイント★
お湯は活用の場が沢山あります。(差し湯、少量の湯冷ましが欲しい等々)
沸騰するまでには時間ががかり、いざ使いたいときに沸騰するまで待つなんてことしたくない!
それ故、料理で一番にすることは”お湯を沸かす”です!!
ケトルであれば、沸騰したら放置で良いのでおすすめですが、
勿論やかんでも構いません。
ポテトサラダ、野菜の出汁煮
じゃがいもを乱切りにする

ポテトサラダを作るためだけに、時間をかけるのは勿体ない!一緒に野菜も煮込みましょう。
※アレルギーが気になる食材は、一度食べて問題ないことを確認するまでは個別に処理しましょう
冷凍のカット済野菜を出汁パックに入れる
お鍋で湯がく際に種類別にとりわけ不要であれば、出汁パックは不要です。
直接お鍋に食材を入れてください。
今回はじゃがいもと分けて作業するため、出汁パックに入れています。
★ポイント★
野菜は離乳食向けのものであればなんでもOK。
よくあるのは人参、玉ねぎ、ブロッコリー、カリフラワー等々。
スーパーで色んな種類の野菜がカット済&冷凍で販売されているので、
それを活用すると下処理の手間が省けて時短になります。
じゃがいもと野菜パックをお鍋に入れて和風出汁で煮込む
離乳食なので、粉末の出汁は昆布やかつおがおすすめ。
具材が柔らかくなるまで、20分程度煮込む。
じゃがいもをフリーザーバッグに入れ、上からつぶす
つぶすのは手でも、平たい器でもOKです。
フリーザーバッグの上からお箸等で1回分の大きさに筋を入れる
何等分にするかはお好みですが、冷凍した離乳食は
1週間を目途で使い切るようにしているので、私は6等分にして使っています。
★ポイント★
あらかじめ筋を入れておくことで、
冷凍して硬くなった状態でも、簡単にパキッと折れて1回分が取り出せます。
こんな感じ!(写真はバナナです)

アレンジ方法
①そのまま食べる。
②刻み野菜や、野菜のベビーフードと混ぜる
混ぜることでバリエーションができるので食べ飽きません!
初めから混ぜて作ると、お子さんの好みによっては、食べ進まないかも。。
そうなると、折角作ったのに…という気持ちが湧いてしまいますし、手間も生じます。
後から混ぜることで、”気に入らない組み合わせなら、もうしない”という選択が簡単にできます。
色々なものを試してみて、お子さんの好みの組み合わせを見つけてみてください♪
柔らかくなった野菜を刻む
大きさは子供の食べ進み具合によって変えます。
中期なら3~5mmが目安です。
野菜が1種類ならポテトサラダと同様にフリーザーバッグでつぶしてもOK。
ただ、折角煮込むなら複数の野菜を同時に煮込んだ方が効率的です!
食べやすい大きさにしたら、フリージング容器に入れる

さてさて、じゃがいもや他のお野菜を煮ている間、手が空きます。
この隙間時間で、バナナペーストを作りましょう。
コンロが複数あれば、大人用の作り置きおかずも並行して作れますよ!
バナナペースト
バナナを適当な大きさに分けて耐熱容器に入れる
バナナの大きさにもよりますが、4,5つくらいに折って入れます。
電子レンジで30秒加熱
バナナをフリーザーバッグに入れ、上からつぶす
つぶすのは手でも、平たい器でもOKです。
フリーザーバッグの上からお箸等で1回分の大きさに筋を入れる
ポテトサラダと同じ要領です!前掲の写真を参考にしてください。
以上がポテトサラダ+αの作り置きでした!
一度、図解を参考に試してみてください。
こちらが参考になれば嬉しいです。



コメント